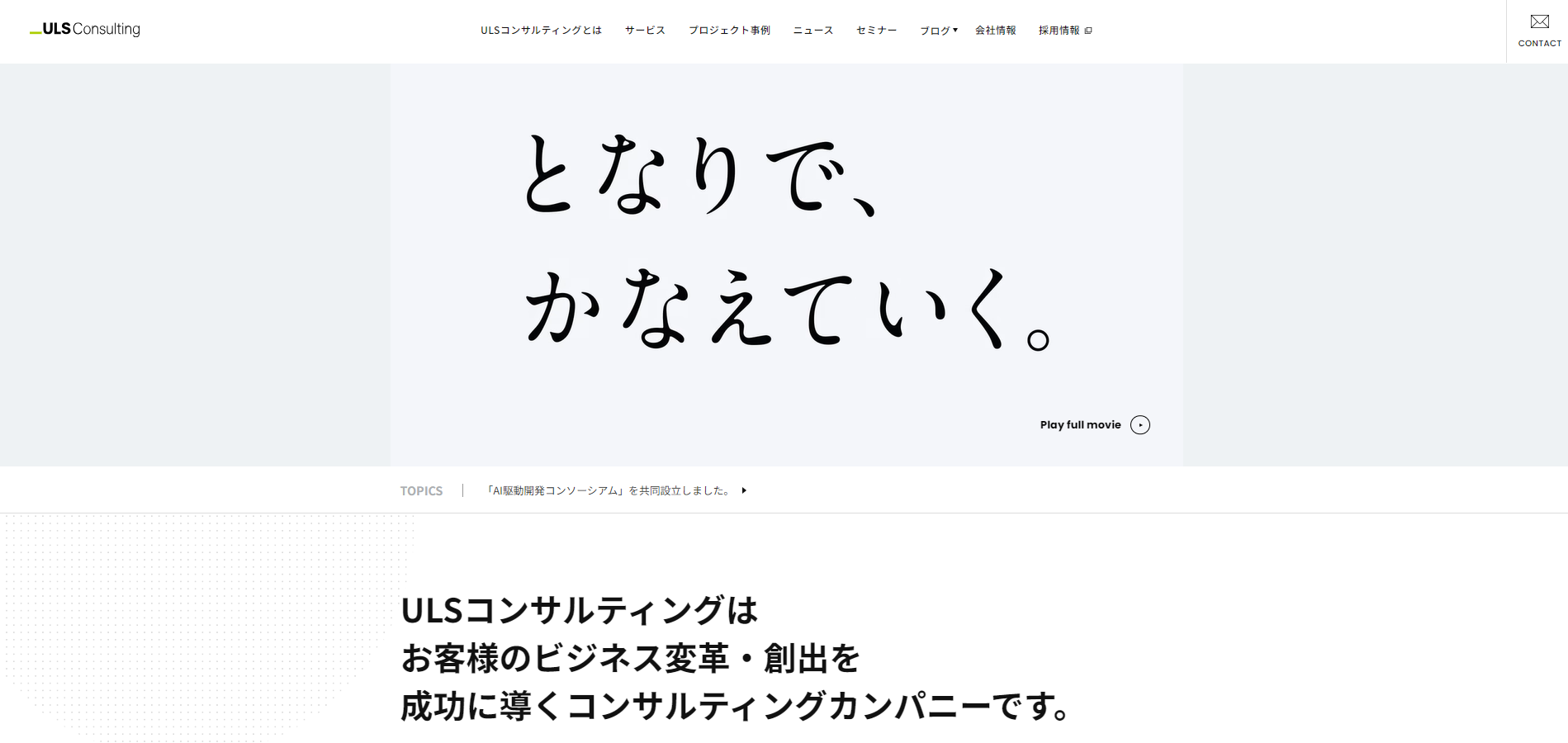基幹システム開発に必要な費用
基幹システムの種類
基幹システムにはさまざまな種類があり、自社の業務内容や規模、将来的な展望に合わせて選定することが重要です。ここでは、代表的な基幹システムについて、その特徴や活用ポイントを紹介します。
ERP(統合基幹業務システム)
ERP(Enterprise Resource Planning)は、販売、在庫、会計、人事など、企業の基幹業務を一元管理できるシステムです。各部門で情報を共有できるため、業務の効率化や経営判断の迅速化に役立ちます。中堅企業から大企業まで幅広く導入されており、最近ではクラウド型ERPも登場し、初期コストを抑えつつ導入できるケースが増えています。
業務の属人化を解消したい、複数拠点や部門をまたいだ情報連携を強化したい企業に適しています。
会計管理システム
会計管理システムは、仕訳・決算・請求書発行など、会計業務を効率化するためのシステムです。企業規模や業種に応じた多彩なパッケージが存在し、法改正対応や税理士とのデータ連携などにも強みがあります。
月次・年次決算をスムーズに進めたい企業や、経理部門の負担を軽減したい企業に向いています。
販売管理システム
販売管理システムは、見積・受注・発注・売上・在庫管理までを一気通貫で管理できる仕組みです。営業部門と在庫・物流部門の連携が取りやすくなり、受発注ミスや在庫不足・過剰のリスクも減らせます。
商材数が多い・取引先が多い企業や、業務プロセスを自動化したい企業に適しています。
生産管理システム
生産管理システムは、製造業における生産計画・進捗管理・原価管理などをサポートするためのシステムです。原材料の手配から工程の進捗、納期管理までを一元管理することで、納期遅延やロスの削減、現場の見える化が実現します。
製造現場を持つ企業や、複数工場・多品種少量生産を行う企業におすすめです。
人事・給与管理システム
人事・給与管理システムは、従業員の情報管理や給与計算、勤怠管理などを効率化するシステムです。従業員データの一元管理や、法令改正への自動対応、テレワーク対応なども充実しています。
従業員数が増えてきた企業や、複雑な勤務形態・給与体系に対応したい企業に最適です。
基幹システムの費用内訳
基幹システムの導入や開発には、さまざまな費用が発生します。費用の内訳を理解することで、予算の適切な配分やコスト最適化につながります。ここでは、基幹システムの主な費用項目について詳しく解説します。
初期導入費用
システム導入時に発生する「初期費用」には、要件定義や設計・開発、システム構築作業が含まれます。パッケージ型であれば比較的安価(数十万円~数百万円)、スクラッチ開発や大規模カスタマイズを伴う場合は数千万円以上かかるケースもあります。また、ハードウェア(サーバーやネットワーク機器)を自社で用意するオンプレミス型は、さらに設備投資が必要です。
カスタマイズ・追加開発費用
業務内容に合わせたカスタマイズや機能追加を行う場合、別途費用が発生します。追加機能の規模によっては、1件あたり100万円~1,000万円程度かかることもあります。標準機能だけで対応可能か、どこまでカスタマイズが必要かを事前に見極めることが重要です。
ソフトウェア・ライセンス費用
クラウド型(SaaS)では月額課金(1ユーザー数千円~数万円)、オンプレミス型では購入時にライセンス費用が発生します。利用ユーザー数や機能数に応じて料金が変動するため、想定利用規模をしっかり確認しましょう。
データ移行・テスト費用
既存システムやエクセル等からのデータ移行、運用テストにも費用がかかります。データ量や複雑さによっては数十万円~数百万円単位になることもあり、移行作業を軽視しないことが肝心です。
教育・トレーニング費用
システム導入後、従業員への操作教育やトレーニングを実施する必要があります。オンライン・対面・マニュアル作成など、実施内容によって費用が異なりますが、運用定着のためにも予算計上しておくと安心です。
運用・保守費用
システム稼働後には、月次または年次で運用・保守費用がかかります(目安:初期費用の10~20%/年)。ソフトウェアのバージョンアップや障害対応、法令対応などが含まれます。クラウド型では保守費用込みのケースが多いですが、オンプレミス型は別途見積もりになることもあります。
隠れたコスト・追加費用に注意
導入後、業務変更や法改正などにともなう追加開発費、ユーザー追加ライセンス費用、外部サービスとの連携費用など、「想定外のコスト」が発生する場合もあります。長期的な運用も見据えた費用管理が大切です。
システム開発の費用を抑えるコツ
基幹システムの導入や開発には多額のコストがかかるため、いかに無駄な出費を防ぐかが重要なポイントとなります。ここでは、費用を抑えつつ、効果的なシステムを導入するためのコツや実践的な方法を紹介します。
必要な機能の明確化と要件整理
最初に「本当に必要な機能」と「将来必要になる機能」を整理し、優先順位を明確にしましょう。不要な機能まで盛り込むと、開発コストが大きく膨らみます。要件定義の段階で現場の声を集め、ムダや重複を省くことが費用削減の第一歩です。
パッケージソフトの活用・カスタマイズの最小化
標準機能が豊富なパッケージソフトを選び、カスタマイズを最小限に抑えることでコストを大幅に削減できます。業務フロー自体をシステムに合わせて見直すことで、無駄なカスタマイズが不要になる場合もあります。パッケージとスクラッチ開発のコスト差は非常に大きいため、比較検討は必須です。
段階導入(フェーズ分け)による初期負担の軽減
すべての機能を一度に導入するのではなく、必要な機能から段階的に導入することで、初期投資の負担を分散できます。まずはコア業務からスモールスタートし、運用状況や現場のフィードバックをもとに徐々に拡張していく方法も有効です。
複数社からの見積もり・比較検討
システム会社やベンダーごとに、提案内容や費用感は大きく異なります。必ず複数社から見積もりを取り、コストやサポート体制、納期、実績などを総合的に比較しましょう。価格だけでなく、アフターサポートや保守体制の充実度も要チェックです。
補助金・助成金など公的支援の活用
国や自治体によるIT導入補助金や助成金など、公的支援制度を活用することで、実質的な負担額を抑えることができます。制度ごとに条件や募集期間が異なるため、計画的に情報収集・申請を行うことが大切です。
トータルコスト(TCO)を意識した選定
初期費用だけでなく、運用・保守、追加開発など長期的な総コスト(TCO:Total Cost of Ownership)も考慮して選定しましょう。目先の安さだけで判断すると、後から予想外のコストが発生しやすくなります。長期的な運用や将来の拡張も見据えて、無理なく続けられるシステムを選ぶことが重要です。
自社に最適な基幹システムの選び方
事業規模・業種ごとの最適なシステムとは?
基幹システムの選定にあたっては、企業の規模や業種に合わせた選定が大切です。
例えば小規模の企業ではリソースなどもが限られていることがあるため、簡便さやコスト効率に優れたシステムを選ぶことがおすすめです。また、中規模の企業の場合は将来的な成長を見越して機能の拡張性がある製品を選ぶという選択肢もあります。大企業の場合は、多拠点での運用やグローバル対応が可能かなどの観点からシステムを選定することがおすすめといえます。
コスト・機能・カスタマイズ性のバランスを考える
基幹システムの導入にあたっては、コストと機能のバランスが取れているか、という点も確認することが大切です。さらに、自社の業務形態やプロセスなどに合うようにカスタマイズを行う必要が生じるケースもあります。ただし、カスタマイズを行うには高額な費用が必要となるため、要件や予算と照らし合わせて検討することが必要です。
失敗しないベンダー・開発会社の選び方
システムの選定・導入計画などの導入サポートが整っているか、もしトラブルが発生した場合のサポートといったように、さまざまな支援が用意されているかを確認することがおすすめです。また、いくつかのベンダーや開発会社と話をすることにより、それぞれの強みなどを把握できます。
基幹システム導入のステップ|成功のためのプロセス
現状の課題を整理する(要件定義の重要性)
はじめに、自社が抱えている課題の整理を行います。システムの導入によってどのような課題を解決したいのかという点を明らかにしておきます。
ベンダー選定・見積もりの取り方
ベンダーを選定する際には、複数のベンダーを比較検討することが大切です。選定する際には、デモンストレーションやこれまでの導入実績、カスタマイズ、サポート体制などの点について確認することがポイントとなってきます。
運用・保守を考えた長期的な視点での導入戦略
基幹システムの導入後は、運用や保守が必要となってきます。導入時にはどうしても導入完了までのコストに目が行きがちですが、運用・保守に関しても考慮することが必要です。この点については、導入時にベンダーのサポート体制が充実しているか確認することがおすすめです。